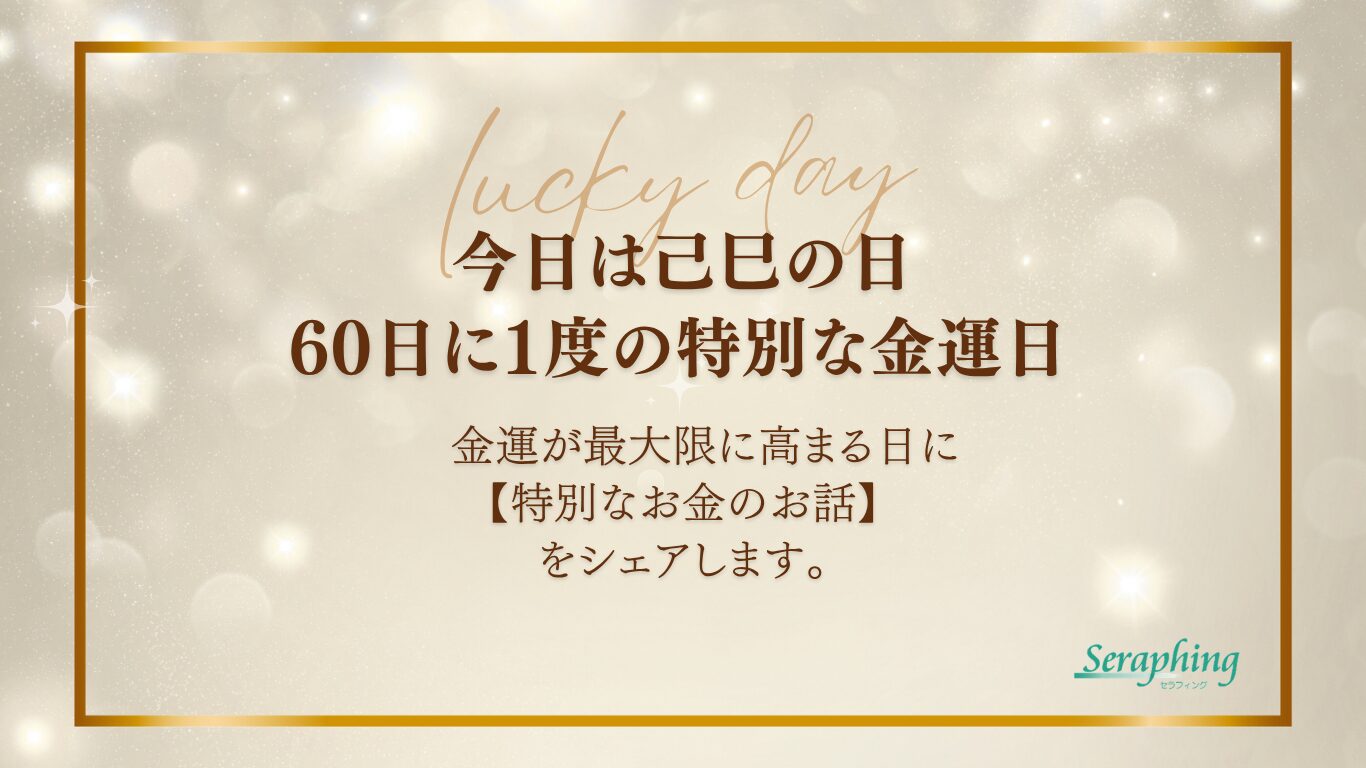「子どもの教育費=学資保険」という考え方は、もう古いかもしれません。資産運用初心者の方は、利率や柔軟性の面で必ずしも学資保険がベストではないことを知っておくべきです。この記事では、教育費を準備する3つの方法を比較し、初心者が安心して選べる考え方を紹介します。
✨このブログは【金運吉日】に合わせて更新しています。教育費を考える特別な日に読むことで、将来への安心が広がります。
1.学資保険の特徴と注意点
1-1. 返戻率と利率の実態
学資保険は「安心」と思われがちですが、返戻率は昔に比べて下がっており、インフレにも弱いのが実態です。利率だけで考えると、他の方法に劣る場合もあります。「入っていれば安心」ではなく、数字を確認して判断することが大切です。
1-2. 途中解約リスク
学資保険は長期契約が前提で、途中で解約すると元本割れするリスクがあります。将来の予定は変わる可能性があるため、柔軟性に欠ける点は要注意。安心のために契約したつもりが、後で負担になることもあるのです。
2.教育費の代替手段
2-1. NISAを活用した積立
教育費の準備方法として、NISAを活用した積立は有効です。非課税で運用でき、複利の効果を活かしやすいため、長期的に資産を増やせます。子どもの成長と同じく時間を味方につけられるのが大きな魅力です。
2-2. iDeCoとの違い
iDeCoも税制優遇がありますが、60歳まで引き出せない点が教育費には不向きです。教育費は10年、15年といった中期で必要になるため、流動性のあるNISAの方が適しています。制度の特徴を理解して選ぶことが安心につながります。
3.投資信託を使った教育費準備
3-1. 分散投資のメリット
投資信託を使えば、株や債券など複数に分散できるため、リスクを抑えつつ教育費を準備できます。一つの商品に依存しないことが、安定した資産形成には不可欠です。
3-2. 途中で引き出せる柔軟性
投資信託の大きな強みは、必要に応じて途中で解約できる柔軟性です。学資保険では元本割れリスクがある一方、投資信託は状況に応じて引き出しや積立額を調整できるので、ライフプランの変化に対応しやすいのです。
4.銀行より証券会社を選ぶ理由
4-1. 商品の豊富さ
証券会社では数千本の投資信託から選べるため、教育費の準備に適した商品を見つけやすいです。学資保険のように選択肢が限られていないので、目的に合わせて最適な組み合わせを作れます。
4-2. 手数料の違い
銀行や保険会社の商品は手数料が高めに設定されていることもあります。一方、ネット証券では低コストの商品が多く、長期の積立には大きな差が出ます。手数料を抑えることも、教育費を守る工夫のひとつです。
5.目的に合った選択をするコツ
5-1. ライフプランに合わせて選ぶ
教育費の準備方法は「これが正解」というものはなく、家庭のライフプランによって変わります。安心を優先するのか、増やすことを重視するのかを考え、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
5-2. 相談を活用する
「どの方法を選べばいいのか分からない」という場合は、独立系ファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。第三者の視点からアドバイスをもらうことで、自分に合った教育費の準備方法がクリアになります。