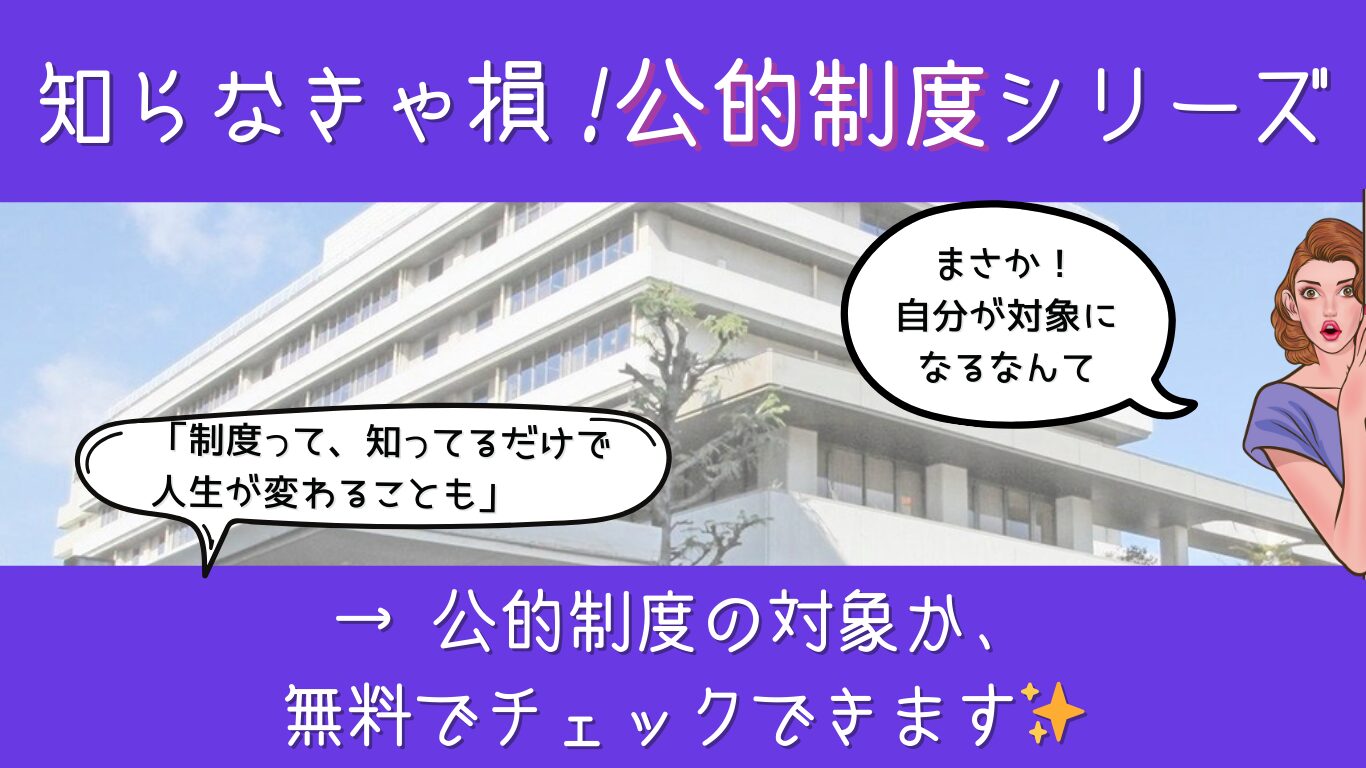「介護してる家族を扶養に入れるといいらしい…」
そんな噂を聞いたことはあっても、具体的な手続き方法や金額のイメージがわかず、そのままにしている人も多いのでは?
実は、たった一つの制度活用で、最大5年分・約50万円の税金還付が受け取れることも。
今回は、制度を使って還付を受けたリアルな事例をもとに、「初心者でもわかる国の制度活用のヒント」をやさしくお伝えします✨
※中立の立場でサポートするAFP(ファイナンシャル・プランナー)が監修しています。
1. 扶養控除とは?
1-1 扶養控除の意味と基本ルール
扶養控除とは、家族を経済的に支えている人が、税金の負担を軽減できる制度です。対象は16歳以上の子どもや親族で、年収の条件や同居・別居によっても変わります。控除額は1人あたり38万円~63万円と大きく、確定申告や年末調整で申請することで税金が戻る仕組みです。
1-2 介護している家族も対象になるの?
はい、介護をしている親や祖父母も条件を満たせば対象になります。特に「生計を一にしていること」がポイントで、同居または生活費の援助があればOK。介護認定や障害者手帳があると、障害者控除が上乗せされることもあります。
2. 実例紹介:5年で約50万円還付!
2-1 Mさんのケース:家族を支える中での気づき
横浜市在住のMさん(30代・会社員)は、お祖母様の介護を3人兄弟で分担していました。両親を早くに亡くされ、深いご縁のあるお祖母様。相談の中で「扶養に入れる」制度があることを知り、まずは市役所と税務署で確認。そこから手続きを進めていきました。
2-2 扶養申告後に受け取った具体的な還付額
なんと、5年分の過去分をさかのぼって申告でき、還付されたのは約50万円!しかも今後は障害者控除の申請も可能な状況に。「知らなかっただけで、これほど違うなんて…」とMさんも驚かれていました。正しい知識が、安心へとつながるのです。
3. なぜ制度を使っていない人が多い?
3-1 情報不足で損している人がほとんど
制度は「知っている人だけが得をする」状態になってしまいがち。学校でも会社でも、こうしたお金の制度は学ぶ機会が少なく、周囲に詳しい人もなかなかいないため、手を出しづらいのが現実です。特に親の介護が突然始まった方ほど、見落としがちです。
3-2 誤解されやすい「年金受給者」との関係
「年金をもらってるから、もう扶養にできない」と思っている方も多いのですが、実は年金収入のみで一定額以下であれば、扶養に入れるケースもあります。年金額や生活の実態によって条件が異なるため、確認してみることが大切です。
4. 初心者こそ制度から始めよう
4-1 投資の前に「守るお金」を整える
資産運用というと「増やす」が注目されがちですが、まず必要なのは「守る」こと。税金の戻りや制度活用は、リスクゼロで使えるお金を増やす手段の一つ。公的制度の活用こそ、初心者が最初に取り組むべき“賢いお金の使い方”です。
4-2 制度活用で生まれる資産運用の余力
例えば、還付された50万円をそのまま積立NISAに回すと、将来的に100万円以上になる可能性も。制度を使いこなすことで「運用資金を作る」ことができ、家計にも安心感が生まれます。守りと攻めのバランスを意識しましょう。
5. 制度を知る・使うために
5-1 自分に合った制度がわかる無料チェック
「もしかして、うちも使えるかも?」という方には、無料で受けられる公的制度診断がおすすめです。扶養控除だけでなく、障害者控除や介護保険制度、医療費控除などのチェックができます。まずは、自分が対象かどうかを知ることから始めましょう。
5-2 迷ったらプロに相談!安心できる一歩を
制度は複雑で、一人で調べるのは限界があります。「何が使えるかわからない」「申請のやり方が不安」という方は、専門家に相談することでスムーズに進みます。LINEで無料相談も受付中ですので、気軽にお声かけくださいね。
実際に制度活用のポイントや、事例の裏側をわかりやすく解説した【賢約サポート代表 薮内裕子氏によるYouTube動画】もご用意しています🎥
「制度ってこんなに使えるんだ!」と目からウロコの内容です✨
ぜひご覧ください👇
👉 YouTube動画はこちら
実際に制度活用のポイントや、事例の裏側をわかりやすく解説した【賢約サポート代表 薮内裕子氏によるYouTube動画】もご用意しています🎥
「制度ってこんなに使えるんだ!」と目からウロコの内容です✨
ぜひご覧ください👇
👉 YouTube動画はこちら